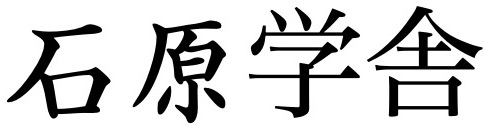チェロの右手親指について
弓先で音を出す時に親指に負担がかかるのをどうにかしたい,親指が痛むのをどうにかしたい,と思うのは多くのチェリストの望みであるようだ.しかし,これに抜本的な解決策はない.そもそも親指の構造が(骨格的にも筋肉的にも)頑丈であるか,そのように身体的に恵まれているのでなければ筋肉を鍛え,身体を上手に使い,親指先のタコが硬くなるまで時間をかけて練習するしかない.プロであれば後者のような身体構造であっても時間をかけてどうにかするしかないが,後者の身体構造を持ったアマチュアの場合は適当なところで諦めることになる.人生において大切なのは程々の妥協である.
それは認めた上で,親指にかかる力についてのネット上の情報や,チェロ教師の教えている内容には明らかに誤っているものがある.大部分のチェロ教師は高校1年生レベルの初歩的な力学の知識すら持っていないし,チェロの生徒も大部分は高校物理での苦い経験しか持っていないはず.ここでは,弓先で弾く時,そして弦に力をかける時(圧力という言葉がすでに力学として意味がない),右手の指にどのような力が必要であるのかをシンプルなモデル計算で示してみた(高校1年物理基礎レベル).中指と薬指の及ぼす力は考慮していないが,これは小指の力の大きさと位置を調整することで簡単に補正でき,本質的な問題にはならないから.以下の図において,力はすべて弓の方向と直交する方向を考えている.弓の方向については問題とすべきポイントがない.

計算結果を解説すると次のようになる.
弦にかける力を大きくすることはFを大きくすることに対応している.このとき,人差し指と親指の力はいずれもFが大きくなると直線的に大きくなる(以後,ある力や距離を変化させる時,他の力は変えずに考える).これは経験的にも理性的も当然の結果である.
分母にあるl_2-l_1は人差し指と親指の距離である.弦にかける力は,本質的にテコの力の応用であるということだ.この距離が短いと,人差し指・親指両方に要求される力が大きくなる.これも経験的・理性的に当然の結果.
弓先で弾くことはxを大きくすることに対応している.このとき人差し指と親指の力はいずれもxに対して直線的に大きくなる.弓先で弾く時に力が必要なのは経験的にも理性的にも当然である.
小指の力については誤解が広まっている.ヴァイオリンは小指を弓の上に乗せ,チェロはフロッグの腹にくっつける.この理由は,小指の重さを弓にかけるためではない.そうではなく,弓先において上の方向に引っ張ることで,他の指の負担を減らす(これもテコの原理の応用)ことが目標なのである.もし小指の力を下向きにかけてしまったら,弓先が上がってしまって逆効果になる.古のチェロ弾きが本当にこれを目指してこのような持ち方にしたとは思えない(今のチェリスト以上に,力学の知識なんかないはずだから).経験的に,なんとなくそうした方が弾きやすいと思ったのであろう.あるいは,小指を乗せると上腕の回内が大きすぎると気づいたのかもしれない(ヴァイオリンの場合は肘の位置がそもそもそんなに高くないので,いっぱい回内しても問題がない).昔習っていた先生が,「弓先では小指で弓の方向に引っ張る」と言っていて意味不明だったが,正確には小指で弓を上に引き上げる(弓が反時計回りに回転する方向にトルクをかける)ことで,他の指の負担を減らす,ということであったのだ.正確な言葉遣いをしてくれないと,何が何だかわからない.音楽教師は最低限の力学を学んでほしい.
他に見かける誤解は,人差し指で弦に力をかけるようにしているのに,親指で反対向きの力を与えたら意味がない,というもの.これは完全に間違っている.親指の力がなかったら,弓は時計回りにまわってしまう.これは,偶力のモーメント,と呼ばれるもので,力が釣り合っていても回転トルクは与えられる,というもの.車のハンドルを直径の両端のところで握って,右手は下に,左手は上に動かそうと力をかけると,両手によるハンドルへの力は釣り合うが,ハンドルは時計回りに回転するでしょ.そゆこと.上の計算でわかるように,弦にかかる力を大きくするためには,人差し指と親指両方の力を増やさなくてはならない.小指を使うと,これらを少し緩和することができる.もし弓先で弾くコツがあるとすれば,このくらいのものだ.